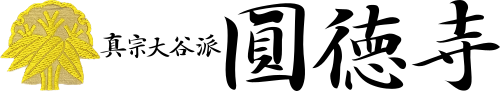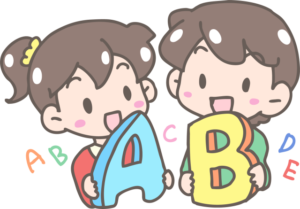僧伽 住職日記
住職日記
仏教は人間の死と長らく向き合ってきました。そしてその死は「人間が死ぬ」という一般論の死でなく「この私が死ぬ」または、「愛する者が死ぬ」という実存的な死と向き合ってきた歴史であると思います。
いつかは皆死ぬのだから受け入れて生きるしかない、などと平時では言えても実際に現実になるとなかなかそうはいかないのが「私の死、愛する者の死」です。
お釈迦さまには愛する者の死に悲しむ方への説法で有名なお話があります。
幼子を亡くしたキサーゴータミーは、悲しみに打ちひしがれていました。自分にとっての唯一の肉親。大切に大切に育てていた我が子。
「どうして私だけこんな目に合わなければならないのか!?」
嘆き悲しむ彼女は、現実を受け止められませんでした。
そして彼女は、村中を訪ね歩きました。「どうかこの子を生き返らせる薬を下さい」と、幼子の躯を抱きながら……。
彼女の境遇を知る者にとっては、彼女の行動は理解できなくはありません。
しかし、幼子の躯を抱きながら「生き返る薬をください」と、突然訪ねてきた彼女を見て、村人はどう思ったでしょうか?
真剣に彼女に取り合ってくれる人はほとんどいなかったことでしょう。中には親切な人もいたでしょうが、生き返らせる薬なんて土台無理な話です。
そうして幼子の躯を抱きながら彼女は、各地を彷徨い続けました。
そんな中、ある家を訪ねると「私はあなたの望む薬は持っていないけど、きっとお釈迦さんならあなたに薬を与えてくれる」と言われました。
そうして彼女はお釈迦さんと出会いました。
彼女はお釈迦さんに「この子を生き返らせる薬をください」と訴えました。
お釈迦さんは「わかりました。その薬を作るには芥子の実が必要です」と言いました。更に付け加えてお釈迦さんは言いました。「ただし、その芥子の実は今まで死者が出たことのない家からもらってくる必要があります」と。
そこで彼女は家々を訪ねました。「芥子の実を分けてくれませんか?」と。
芥子の実ぐらいであれば、香辛料としても使われるため、どこの家にもある代物です。 「いいですよ」と言ってくれる家はたくさんありました。
しかし、彼女は問います。「今までこの家から死者はでてないですか?」と。
すると家の人は応えます。「実はこの間おばあちゃんが……」と。
そこで次のお宅へ向かい、また同じように尋ねました。「今までこの家から死者はでてないですか?」
「実は何年か前に祖父が……」
「実は何年か前に夫か……」
「この子が生まれてすぐに妻が……」
「何番目の子供が事故で……」
「数十年前には父方の母が……」
「そういえば父方の母の姉が私の生まれる前に…」
そんなこと言えば、両親、祖父母、そのまた前……、死者の出ていない家なんてあるはずありません。 彼女は、各家を訪ね歩くうちに気がつきました。
「死は誰にでもやってくる。自分だけが特別不幸に見舞われたわけじゃない。誰もがそのような苦しみを背負っていたんだ……」そして、彼女は抱いていた子供の躯を弔い、自分自身の人生を再び歩み始めました。当たり前のことに気づかせてくれた、お釈迦さんの弟子として。
この話は諸行無常を教える説話として有名です。私はこの話を聞いて大切なのはキサーゴータミーが愛する人をなくして悲しみを持って生きるたくさんの方に出会っていかれた事だと受け取っています。 おそらく訪ねた家の方といろいろ話をされたことと思います。その歩みの中で悲しみの心と向き合えたのだと思います。お釈迦さまの説法はキサーゴタミーが村中の家を回るその歩み全体なのです。
念仏は人の歩む相を通して教えが伝わってきました。キサーゴタミーも悲しみを持ちながら先に歩まれている方に出会っていかれました。ただ念仏の教えに私の思いや解釈をつけるのはよくないと知りながら、それでも意味を求めてしまう私の思いでは、念仏は仏様と出偶うことといただいています。
仏様と言ってもすごい方とか亡くなられた方というより、人生を歩む相をもって私に大切な事を伝えてくださる方の事です。私の深きご縁となって導てくださる方を仏さまとしていただいていけることが有難いと感じています。